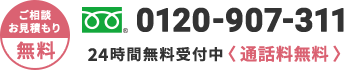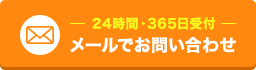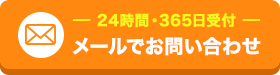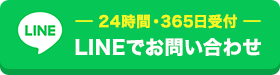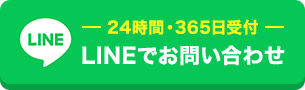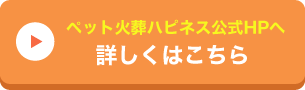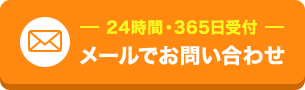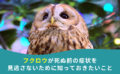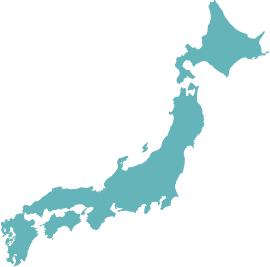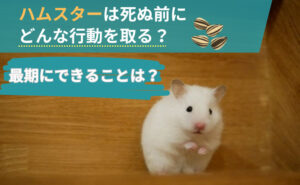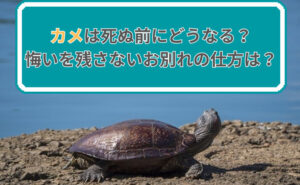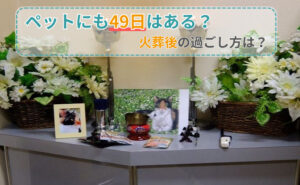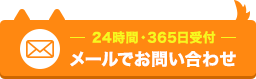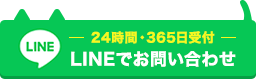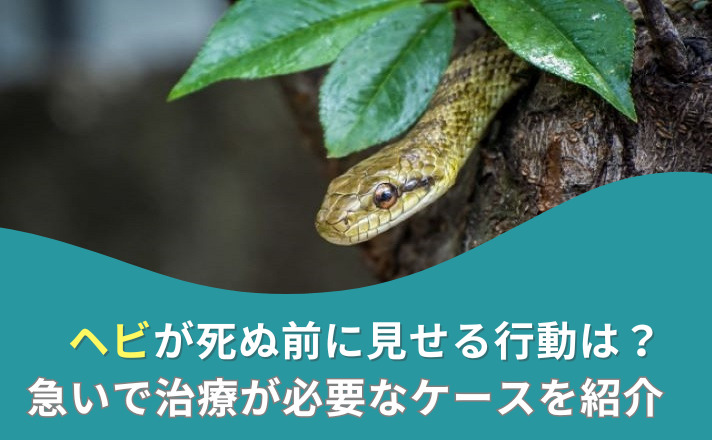
ヘビは大人しい生き物で、じっと動かないままで居ることも多いです。
しかし、動かない理由はヘビ自身の性格や性質以外にも、病気やケガで動けなくなっていることも考えられます。
そのため、ヘビの不調には飼い主様自身が早めに気付いて、対処してあげる必要があります。
このページでは不調を抱えたヘビの様子や対処方法、見送り方について紹介します。
大切なヘビを見守り、必要な時は手助けできる知識を身につけるのに役立てば幸いです。

この記事の監修者
高間 健太郎(獣医師)
大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。
ヘビに元気が無い理由と対処方法

大切なヘビに元気が無い場合、病気や死ぬ前のサインなど嫌な予感がよぎるもの。
しかし、実際は心配ないことも多いです。
この章ではヘビに元気が無い場合に考えられる原因と、対処方法について紹介します。
元々動かない性質
ヘビは元々活発に動き回りません。
動かなくても元気な場合も多いです。
毎日観察を欠かさず、異常があればすぐに気付いてあげられる環境作りが大切です。
あまりに動かない状態が続く場合は、室温を確認しましょう。
変温動物であるヘビは室温が下がると動きが極端に鈍くなることがあるためです。
種類にもよりますが、およそ25~30度がヘビの飼育には適温とされています。
ヒーターの設置はもちろん、温度計で適温が保たれているかを確認しましょう。
また、ケージの置き場所は直射日光が当たらず、温度が急激に上下しない場所に設置することもポイントです。
脱皮を控えている
ヘビの脱皮はエネルギーを使う作業のため、脱皮を控えたヘビはまったく動かなくなります。
脱皮のサインとして、エサを食べなくなる、目が白く濁るなどの変化が見られるようになるため、脱皮しやすい環境を整えてあげましょう。
基本的には環境を整えて無事に終わることを祈ることになります。
ケージ内の湿度を60~70%と少し高めにしておくと脱皮しやすくなるようです。
また、ヘビの好みにあわせて体が浸かる水、体を引っかけて皮を脱ぎやすくする木などを用意してあげましょう。
今すぐに対処が必要な、ヘビが死ぬ前のサイン

次に紹介するような異変が起こっている場合は、ヘビが弱って体力が尽きかけている、病気になっているなど、命の危険が迫っている可能性があります。
呼吸がおかしい、音がする
ヘビは声帯を持っていないため、犬や猫のように鳴き声を出すことは出来ません。
そのため、呼吸する音がずっと聞こえていたり、口を開けっ放しにして口呼吸をしている場合は、呼吸に異常がある可能性があります。
肺炎などの病気にかかっている場合や、マウスロットと呼ばれる口内炎の一部が悪化し、口が閉じられなくなっている可能性もあります。
脱皮に失敗している
脱ぐはずだった皮が体に残ったままの場合も注意が必要です。
残った皮の影響で血行が悪くなり、次の脱皮の際に脱皮を失敗する範囲が広がる、悪い場合は壊死してしまうなどの可能性があります。
落ち着かない、尻尾の辺りが膨れている
メスのヘビの場合、卵詰まりを起こしている可能性があります。
その他にも食欲が極端に落ちる、排せつしにくくなるなどの異変が見られます。
一匹で飼育している場合でも、無精卵を身ごもるケースもあるため注意が必要です。
危険なサインを見かけたら早めに病院へ
ネットでは脱皮を手伝う方法など様々な解決方法が見つかりますが、無茶な治療はヘビの寿命を縮めてしまいます。
そのため、ヘビが体調を崩した場合は、早めに病院に行きましょう。
ヘビの見送り方

ヘビが体力の限界を迎えた場合は、できる限りそばで見守ってあげましょう。
そして、ヘビが旅立った後は感謝を込めてお見送りをします。
ヘビは火葬がおすすめ
ヘビの遺体は火葬するようにしましょう。
きちんと火葬して見送ることで、感謝を伝えて丁寧にお見送りできます。
見送り方には他にも土葬や燃えるゴミとして出すことなどの選択肢もあります。
しかし、よく考えず選ぶと環境に悪影響を与えたり、お別れに後悔が残る可能性も高いです。
【お見送りまでの流れ】
火葬の際は、以下の流れでお見送りします。
| 必要な作業 | 作業内容 |
| 遺体の安置 | ヘビの体をきれいにして、棺に納める。 その後、傷まないように保冷剤で冷やす |
| 火葬を依頼する場所に連絡 | ヘビの火葬は「自治体」「ペット火葬業者」に依頼する |
| ヘビを供養する | 火葬後、大切なヘビの安らかな眠りを祈って供養 |
大まかに上記の3ステップで送り出します。
より詳しい火葬・供養の流れはこちらのページで紹介していますので、参考にしてください。
ハピネスではヘビのお見送りにも多数立ち会ってきました。
その経験を活かして理想通りのお見送りになるようサポートしますので、遠慮なくお申し付けください。
ヘビが死んだ後に必要な手続き
ヘビのお見送りは犬・猫などと同じく、遺体の安置後に火葬を手配することで行います。
しかし、ニシキヘビなど大型のヘビや一部の毒ヘビなど「特定動物」に指定されているヘビの場合は、死亡から30日以内に「飼養・保管数増減届出」の提出が必要です。
特定動物ではないヘビは必要ありませんが、念のため覚えておきましょう。
まとめ
ヘビに元気が無い場合でも、ヘビの性質によっては心配ないケースもあります。
しかし、呼吸音がおかしい場合やお腹が膨れて卵詰まりを起こしている場合は、命に関わる危険なサインかもしれません。
早めに病院に連れて行ってあげましょう。
また、亡くなった後は心を込めて送り出してあげましょう。
お見送り方法はそばで旅立ちを見送れるうえ、供養できる火葬がおすすめです。
この記事の執筆者

ペット火葬
ハピネス 編集部 J・N
愛するペットちゃんとのお別れによって心に深い悲しみと不安を抱えた飼い主様を支えられるような、わかりやすく正確な記事作成を心掛けています。自分のこと以上に大切な家族を思いやることができる優しい心を持った飼い主様の力になれるように努めます。