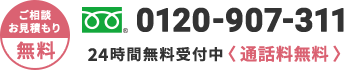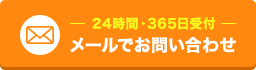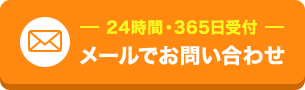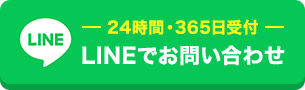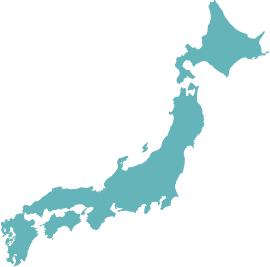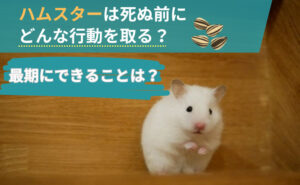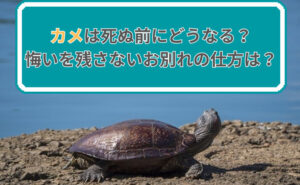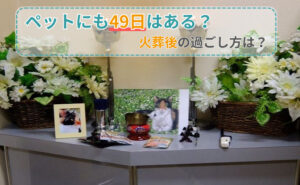猫は体調不良を隠す習性があるため、病気になってもすぐには気付けないことも多いです。
しかし、いつも一緒に過ごしている猫の行動に異変があったら飼い主様はすぐに気づくもの。
その場合は「重い病気じゃないか心配」「すぐになんとかしてあげたい」と思うものですよね。
猫の様子がいつもと違う場合は、まずは観察して体調を崩していないか確認することが大切。
このページでは猫が体調を崩した時のサインや死ぬ前に見せる行動について紹介します。
「元気が無い」「いつもと違う行動を取っている」など、大切な猫に異変があって心配な場合は、このページを参考にして体調を崩していないか確認してあげましょう。
猫が死ぬ前にする行動や変化

実際に猫が死ぬ前にはどのような行動や変化があるのでしょうか。
隠れ場所を探そうとする
「猫は死ぬ前に姿を消す」という言葉を聞いたことはありませんか?
これは弱っているときは人のいないところで回復を待つという猫の習性を表しています。
お家で暮らしている猫の場合は高い場所や狭い場所に潜みたがることが多いようです。
落ち着きなく部屋の中をウロウロして隠れ場所を探している様子が見られた場合は、体調を崩していないか疑った方がいいかもしれません。
たくさん甘えてくる
猫は死ぬ前になると悟ったように、甘えてくると言われています。
猫がいつも以上に甘えてきた場合は、優しく甘えさせてあげましょう。
同時に、体調を崩していないかよく見てあげるようにしましょう。
鳴き声
さっきまで弱っていたのに急に元気になって大声で鳴いたり、聞いたことのないような甘えた声で鳴きながらすり寄ってきたりと、体調を崩した猫は普段と鳴き声が違います。
飼い猫は飼い主とコミュニケーションを取るために鳴くと言われています。
そのため、普段と違う鳴き声で不調を訴えているのかもしれません。
いつもと違う鳴き声を聞いた場合は注意して見守ってあげてください。
ご飯も水も飲まない
死ぬ前はほとんどの猫は食欲がなくなります。
また、水も自力では飲めなくなるため、脱水症状になってしまうこともあります。
獣医師に相談し、必要であればスポイト等で水を飲ませてあげましょう。
目がうつろ
死ぬ前の猫は「目に力が入っていない」「焦点が合わない」などの症状が見られます。
猫が安心できるように、できるだけ見える場所にいて安心させてあげましょう。
お漏らしする
いつもはトイレで用を足していた猫が、場所に関係なくお漏らししてしまうことがあります。
ストレスのアピールの可能性もありますが、トイレまで行く気力を失っているサインかもしれません。
反対に、トイレの中から出てこずに、そこから動かないというケースもあります。
もし猫が寝床などでお漏らしをしたら体が汚れてしまいます。
なるべく早く汚れを拭き取って清潔にしてあげましょう。
口呼吸になる
普段は口呼吸ではないですが、体調が悪い時や死が迫っている時に口呼吸をすることが多いです。
呼吸の乱れがないか意識して見るようにしましょう。
心拍数の減少
猫に死が近づいてくると、心拍数が減少していきます。
猫の胸に耳を当てて音を聞いてあげましょう。
体温が下がる
猫の死が近づくにつれて、体温がだんだん下がってきます。
体温が下がっている状態のときに食事を与えると、嘔吐してしまう場合があるので気をつけましょう
猫の寿命はどれくらい?

猫の寿命は平均12~13歳程度と言われています。
しかし、食べ物や運動などの生活習慣によって異なるうえ、野良猫の寿命は3~5年程度と室内で飼われている猫とは大きな差があります。
猫は生まれてから1年で人間でいう20歳程度になり、その後1年で4歳程度ずつ歳をとっていきます。
つまり、生後6か月までを子猫期、7か月~2歳を青年期、3~6歳を成猫期、7~10歳を中年期、11~14歳を高齢期、15歳~が後期高齢期となります。
人間は60際で還暦ですが、猫は11歳くらいで人間の60歳程度になり、高齢期に入っていきます。
猫に多い死因とは?
近年、猫にも人間同様に生活習慣病が増加傾向にあります。
猫の死因を理解し、日常の習慣を見直せば、長生きにつなげられるでしょう。
ガン(悪性腫瘍)
多様な種類がありますが、猫が特に罹患しやすいのは「皮膚腫瘍」「乳腺腫瘍」「リンパ・造血器系腫瘍」です。
発症要因としては生活習慣、ストレス、遺伝的要素、ホルモンバランス、加齢などが複合的に関与していると考えられています。
早期発見・早期治療により救命できる事例も多いため、定期的な健康診断と異変を感じたらすぐに獣医師の診察を受けましょう。
心臓病
この疾患は子猫から高齢猫まで、あらゆる年齢層で発症する可能性があります。
初期段階では症状が現れにくいものの、病状の進行に伴い「元気消失」「食欲不振」「呼吸困難」などの徴候が現れます。
腎不全
猫は他の動物種と比較して、腎不全による死亡率が著しく高い特徴があります。
腎不全は字義通り、腎機能が失われる疾患です。
腎臓はや血中老廃物の尿排出や水分バランスの調整など生命維持に不可欠な機能を担っているため、その機能低下は他臓器にも広範囲に悪影響を及ぼします。
猫を長生きさせるポイント
猫を長生きさせるためには、病気のリスクを最小限に抑えた環境を作りましょう。
室内飼育の徹底
屋外には猫にとって数多くの危険が潜んでいます。
猫エイズウイルスや猫白血病ウイルスなどの感染症リスク、そして交通事故の危険性もあります。
猫の寿命を延ばすためには、完全室内飼育が最も効果的な選択です。
栄養バランスのとれた食事
日々の食事には「総合栄養食」と明記された、必要な栄養素がバランスよく含まれたキャットフードを選択しましょう。
猫は肥満になりやすい体質を持っています。
過剰な体重は糖尿病をはじめとする様々な疾患リスクを高めるため、食事量やおやつの与え方には細心の注意が必要です。
適切な運動機会の確保
適度な運動は体重管理だけでなく、ストレス発散にも効果的です。
猫は本来、狩猟本能を持つ動物であり、おもちゃを使った遊びを好みます。
特に室内飼育の場合は運動不足になりやすいので、意識的に運動する機会を作ってあげましょう。
ストレスフリーな環境づくり
猫は清潔さを好む動物です。食事スペース、トイレ、寝床など、生活空間の衛生状態を保つことでストレスを軽減できます。
また猫の性格は個体差が大きく、甘えん坊タイプもいれば独立心の強いタイプもいます。
それぞれの性格に合わせたコミュニケーション方法を心掛けましょう。
予防医療の活用
ワクチン接種により、様々な感染症やノミ、ダニ、フィラリアなどの寄生虫被害を予防できます。
また避妊・去勢手術は生殖器系の疾患リスクを低減します。
予防可能な病気は積極的に対策することが、結果的に長寿につながります。
定期的な健康診断
猫は人間よりも加齢のスピードが速いため、健康診断は半年に1回、高齢猫では年に3回程度が理想的です。
日常的な健康観察も欠かさず、少しでも気になる兆候があれば速やかに獣医師に相談しましょう。
猫の最期にできること

猫に最期が近づいたら、猫のためにしてあげたいと思うのは当然のことです。
しかし、具体的に何をしてあげればいいか分からないという方がほとんどだと思います。
この章では猫に最期にしてあげられることをご紹介します。
優しく撫でてあげる
猫は死ぬ直前になると、目が見えなくなることもあります。
近くで見守るだけでなく、優しく撫でて落ち着かせてあげましょう。
また、無理のない範囲で抱っこしてあげるのも良いでしょう。
甘えん坊な性格の猫であれば、抱っこをするだけで安らかな気持ちになれるはずです。
もちろんそっとしておいてほしい猫もいるので、性格に合わせてストレスにならない程度にスキンシップをする、声かけにとどめるなど、飼い主様が判断してあげてください。
声をかける
猫が寂しい思いをしないように、声をかけたり、名前を呼んだりして安心させてあげましょう。
食べたいものをあげる
獣医師より食べ物を制限されていない場合は、好きな食べ物をあげましょう。
食べやすいように細かくしてあげましょう。
好きだったものを近くに置く
お気に入りのおもちゃなど、猫が好きだったものを近くに置いてあげることで、気持ちが落ち着く場合もあります。
寝床を整える
最期の数日間は動かず寝て過ごすことがほとんどです。
排泄物などで汚れてしまった場合は、拭いて寝床をきれいにしてあげましょう。
また床ずれを起こすこともあるので、クッションなどを置いてあげるのもいいでしょう。
高齢期の猫に気をつけること

猫は11歳を過ぎると高齢期に入り、老化が始まります。
猫の場合は一年に人間換算で4歳歳を重ねていくため、ちょっとした変化を見過ごさないようにしましょう。
この章では猫の高齢期に気をつけることをご紹介します。
体重の変化
高齢期になると猫も筋肉が落ち、体重が痩せてくることも不思議ではありません。
しかし、食べているのに極端に体重が減ってきた場合は、病気からくる症状かもしれません。
体重を定期的に計るようにして、どのくらいご飯を食べているか日々確認しておくといいでしょう。
ずっと寝ている
猫は一日の中でトータル12~16時間寝て過ごすと言われており、高齢期になるとさらに睡眠時間が長くなります。
しかし、寝ている時間が極端に増えた場合は、病気や痛みなどを抱えている可能性もあります。
ご飯も食べず寝てばかりいるというような場合は、獣医師に相談するようにしましょう。
また、長時間寝た姿勢のままだと、床ずれを起こしてしまう場合もあります。
一度床ずれになると治りにくいので、定期的に寝返りをさせたり、クッションを圧力のかかりにくいものにするなど、未然に防いであげることが重要です。
鳴き声がいつもと違う
「苦しそうに鳴いている」「大きな声で長時間鳴いている」「興奮したように鳴く」などいつもと違う鳴き方をしている場合は、病気や痛みを抱えている場合もあります。
鳴き声以外におかしなところはないか確認し、必要な場合は獣医師に相談しましょう。
食事の量が減る
猫は高齢になると、人間と同様に食べたものを消化する能力や関節、筋力が衰えてきます。
健康状態に合わせて、ご飯をシニア用に変えたり、おやつを栄養価の高いものや消化のよいものに変えていきましょう。
また、今どのような栄養が不足しているかを見た目から判断するのは難しいため、健康診断などのタイミングで獣医師に相談するのがおすすめです。
うまく階段をのぼれなくなる
高齢の猫は筋力の衰えによって、これまでは難なく越えられた段差の昇り降りが足腰の負担になり、転倒・転落などの危険性も高まります。
高い場所には登れないようにしておく、それほど高くない場所なら箱を階段のように置いて中継点を作るなど、猫が過ごしやすいお部屋にしてあげましょう。
あわせて、室温を一定に保つことで急激な温度変化で体力を消耗しないようにしてあげましょう。
老猫の場合は夏場なら27~28度、冬は25~28度になるように設備を整えてあげてください。
猫が死ぬ前に決めておくといいこと

猫の最期を覚悟していても、実際に大切な家族とお別れする際は誰もが慌ててしまうもの。
この章では、後悔のない最期を過ごすために、事前に決めておいたほうがいいことをご紹介します。
治療について
猫を病気で看取る際は、「もっと治療してあげておけば…」など後悔を抱えることもあります。
どのような形で亡くなっても、辛く悲しいものです。
できる限り後悔が残らないように「どこまで治療するのか」「どこで最期を迎えるのか」など事前に家族で話しあっておくようにしましょう。
最期の過ごし方
猫に病気が見つかった場合、治療とあわせて猫に余生をどこで過ごしてもらうかも話し合っておきましょう。
【家で過ごす】
猫の老化が進んで自力でご飯を食べたり、トイレに行ったりできなくなった場合は手助けをしてあげる必要があります。
不在がちな方はペットシッターの利用を検討するなど、猫の快適な生活のために最適な方法を考えてあげる必要があります。
【入院治療を行う】
病気が重いため入院治療を送ってもらう場合は、最期を看取れない可能性があることを考えておく必要があります。
アイペット損害保険株式会社は2016年8月5日に行った「ペットとのお別れに関する調査」を実施。※1
その中の「ペットとお別れして後悔していることはありますか」という質問に対して「もっと一緒の時間を過ごせばよかった」と回答した猫飼育者が36.9%となっています。
また「もっと健康管理に気を使ってあげれば良かった」との回答が33.8%となっています。
苦しい思いをさせないように「設備が整っている病院で治療して少しでも楽に過ごしてほしい」と考えるのも一つの判断です。
しかし、家族から離れて病院で息を引き取った場合、このアンケートと同じように後悔を抱えてしまう可能性もあります。
「どこで最期の時間を過ごしてもらいたいか」はきちんと話し合っておくことをおすすめします。
【後悔しないお見送りのために】
筆者が飼っていた犬の腎臓の病気が重くなった際、入院はさせずに家で看取ることに決めて、薬を飲ませたりできる限りのことをして見送りました。
その選択自体に後悔はありません。
しかし、たまに「もし入院させていればもう少し楽に旅立てたのでは?」と考えることがあります。
猫のことを考えて判断することも大切です。
しかし、ご自身が後からどう思うかも忘れずに考えてみる事も大切です。
*参考サイト
アイペット損害保険株式会社「ペットとのお別れに関する調査」
葬儀・火葬方法について
猫が亡くなった際は、「私有地に埋葬する」「自治体にて焼却してもらう」「葬儀業者にて火葬する」といった方法があります。
また、葬儀業者に依頼する場合は、個別に火葬する方法や合同で火葬する方法があり、立ち会いをするかどうかも決めることができます。
いざという時に慌てないよう、こちらも事前に決めておくといいでしょう。
また、事前相談を受け付けている業者もありますので、一度問い合わせてみるのもおすすめです。
遺骨の供養方法
最近は猫専用のお墓を作る方や、人と猫が一緒に入ることができるお墓を建てられる方もいらっしゃいます。
また、遺骨をアクセサリーやオブジェなどにする手元供養もあり、事前に供養方法を決めておくと、葬儀業者を選ぶ際にスムーズです。
ただし、猫の場合は遺骨のままご自宅で保管することもできますので、遺骨の供養は落ち着いてからされても問題はありません。
遺骨の供養方法については、以下のコラムで解説しています。
返骨してもらった遺骨をどのように供養したいかお悩みの際は、こちらを参考にしてください。
まとめ
大切な猫の最期を考えることはとても辛いことです。
しかし、いずれ訪れるお別れの際に、心から送り出してあげられるように事前に決めておくことはとても大切です。
そのためにも、どのような最期にしてあげたいか、どのように送り出してあげたいかなど日頃から家族で話し合っておくようにしましょう。